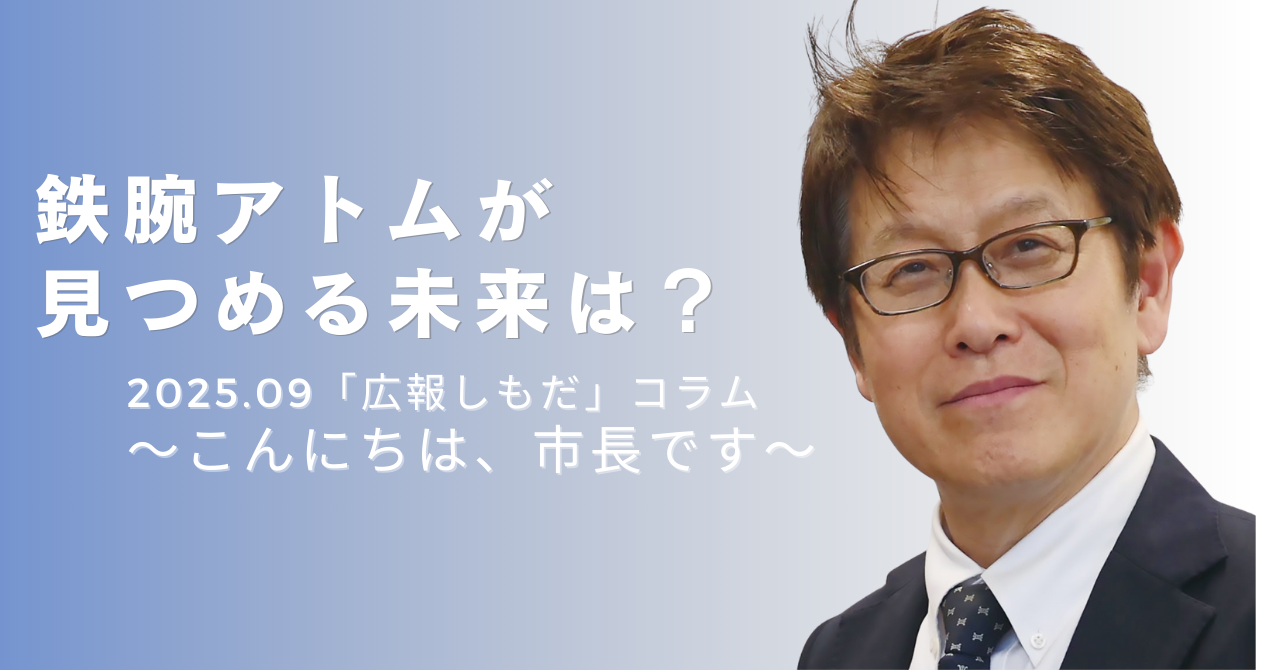下田小学校の校歌(昭和22年)はすごいと思う。ペリー来航から始まり、続く二番では、下田町奉行今村正長公、写真の祖下岡蓮杖(下田生まれ)、そして儒学者中根東里(同じ)と、下田ゆかりの三人の偉人への敬意が示される。今回はこのうちの中根東里にちなんだ話である。
清貧という言葉がこれほど当てはまる人は珍しいそうで、あの(テレビにもよく出演されている)磯田道史先生も『無私の日本人』という著書の中で世界に誇れる立派な人として讃えている。その東里が残した言葉にこういうものがある。
「水を飲みて楽しむ者あり、錦を着て憂ふる者あり」
さて、話は変わるが、今、大阪万博が開催されている。AI(人工知能)やVR(仮想現実)などの展示に多くの入場者で賑わっている。55年前の1970年にも大阪万博があった。当時小学生だった私も見に行った。その時の目玉は「月の石」で、アポロ宇宙船が月から持ち帰ったそれを見るため丸一日行列に並んだ記憶がある。また、日本で初めて広く一般にハンバーガーが売られたこともこのイベントの目玉のひとつだった。TVでしか見たことがない豊かな暮らしの形がそこにはあったように思う。現実的には物価高とか学生運動とか苦しい時代だったが、「太陽の塔」に象徴されるように私たちは明るい未来に向かって「水を飲みても楽しく」生きていたように思う。
そして、今、実際に便利で快適な社会となっているのに、なぜか多くの不安や不満が蔓延している。TVでも毎日聞かされているので、「そうか、そんなにひどい社会なんだ今の日本て」と思ってしまう。
今回の大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。私も行ったが、想像以上に盛り沢山で十分に見物できなかった。ただ一つ強く心に残ったのは、あるパビリオンの屋根の上でポツンと一人海の彼方を指さす鉄腕アトムの姿だった。彼は一体何を指さしているのだろう。善良なAI(という設定⁈)のアトムは何を言いたいのだろう、と思った。そして、その時なぜかふと東里のあの言葉が浮かんだのだ。「錦」(モノ)があふれている一方、不満や分断に覆われている今、どんな「未来社会」をデザインすべきか。私たちはアトムに答えなければならない。